この記事では、護符とはいったいどんな効果を持つもので、お札やお守りとどう違うのか、比較検証した内容をご紹介していきます!
困ったときの神頼みなどといわれて、難問難題に突き当たると何かに頼るというのが人の常。
その頼る手段に護符・お札・お守りがあり、それぞれ違いがあるんです。
護符とかお札とかお守りを、身につける?或いは家の中に祀る?など様々な神頼みの方法があり、その効果ご利益は多岐にわたります。
護符とはいったいどんな効果を持つもので、お札やお守りとどう違うのか、比較検証した内容を知りたい方は必見です。
『護符』ってどんなもの?!
いきなり『護符』と言われても、そもそも何なの?と思ってしまいますよね。
文献によると、次の様に解説されています。
将来生じるかもしれない災厄を予防するために,呪力を帯びたものとして身に着けられる小さな物。
ひとたび呪力が与えられれば,
- 普段は祈願されたり,
- 特別視されたり
することはほとんどなく,したがってその働きは自動的であるので,しばしば呪符と区別されることがあるが,現実にはそれほど厳密な差異はみられない。
先史時代から現在まですべての民族にみられるもので,爪,髪,骨,金,石,布,毛皮,紙などが護符としてよく用いられる。
出典|ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
というようですが、何だこれは?というように難しい説明になっています。
平たくいえば、将来身の回りに起きるだろうとういう厄などの予防に、呪力を帯びた小物を身につけるとで厄を回避することができるというおまじないのようなもの。
護符は霊符とも呼ばれているのです。
そして、護符を作ることができるのは
- 陰陽師
- 仏僧
- 神職
と、いわれているように『呪力に通じたある力』を持つ者に限られています。
呪力に通じた人とは?
まじない、又はのろいの力などといわれていて、特定の人・物・現象などにやどると信じられている超自然的な力が呪力といわれている。
そして、このような能力を持つような人(陰陽師・仏僧・神職などという人たち?)が護符を作ることができると考えられています。
つまり一般的に『霊能力者』と呼ばれる方が気を込めて封印したものを『護符』といっています。
護符の効力
護符(霊符)の種類はこの世の中に300種類以上あるのが現状。
そして、願いに応じて護符を作成してもらい、その護符を身につけるなどして、はじめて護符の効果が出ると言われています。
護符は霊能力者の方が気を封印したものなので、霊能力者の方でも特にお力のある方が作らないと何の意味もないという事。
しかし、護符を持ってるだけで願いが叶うと思われてる人が多いいようですが、護符は持ってるだけで願いが叶うというものではないのです。
護符は本気で願いを叶えたいと、強い思いのある人の願いを叶えてくれるということ。
護符は、本当に効果があるものといわれていて、間違った使い方をしたりすると何の意味もない逆の結果を招いてしまう恐れもあるのです。
護符の力は絶大で強力なお守りであるため、本気で叶えたい願いがある人が護符を持つことで効力が発揮される。
潜在意識を引き出す護符
護符は、カバンの中等に入れて持ってるだけでは残念ながら願いは実現しないのです。
毎日、護符に願いを込めることで自分自身の力を引き出してくれる媒体という事なのです。
したがって、潜在意識に訴えかけて自分自身のもともと持ってる力を引き出してくれるツールという考えかたにもなるようです。
『お札』とはどういうものですか?
良く寺社仏閣を訪れるとお札があります。
そしてお札には、家内安全や火災、疫病といった祈願ごとにより災厄からお守りしてくれるといわれています。
お札は主に神棚にお祀りしたり、門口や柱に貼ったりしています。
では、お札って何なのと改めて考えると本当のところはあまり知られていないようです。
文献によると、次の様に解説されています。
仏のお守り札のこと。
災いを防ぎ,吉善を招く神秘的な力が宿っていると考えられる木札や紙札。
仏寺系の
- 宝印
- 護符
神社系の
- 神符
- 霊符
をさすが現在では
- 開運
- 安産
- 交通安全
- 試験合格
までさまざまなお札がつくられている。
出典|ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
そもそも“お札”とは?
日本では古くから、
- お正月にお迎えする歳神さま
- 台所には竈神さま
- 井戸には井戸神さま
など、さまざまな神さまをおまつりし、日々の暮らしをささえて下さる神々の恵みに感謝してきました。
そして、
- 伊勢の神宮のお神札(神宮大麻)
- 氏神さまのお神札
- 特別に崇敬している神社のお神札
を神棚等にお祀りすることが一般的になってきています。
おまつりする場所はどんなとこ?
お神札をおまつりする場所は、家の内でも家族が集まる清浄なところを選ぶことが良い。
家族がお参りをする『家庭のまつり』は、日常生活における一家の中心となる行事となるからです。
一般的には、
- 清らかで明るく
- 静かで高いところ
- 南向き、あるいは東向き
におまつりするのがよいと言われています。
家族が親しみを込めて、毎日お参りのできる場所を第一に考えて、何よりも、尊ぶ心を持って、日々丁重におまつりすることが大切なのです。
お神札(ふだ)のまつり方
お神札をまつる御神座の順位は、
- 中央を最上位
- 次が向かって右
- その次が向かって左
というようになります。
三社造りの宮形での飾り方
- 中央に日本人の総氏神さまである伊勢の神宮のお神札(神宮大麻)
- 向かって右に地元の氏神さまのお神札
- 向かって左に崇敬している神社のお神札
をお納めします。
その他の神社にお参りをされた際に受けたお神札は、向かって左におまつりした崇敬神社のお神札の後ろに重ねてお納めするなどしています。
一社造りの宮形での飾り方
- 神宮大麻を一番手前
- その後ろに氏神さま
- その後ろに崇敬する神社のお神札
を重ねてお納めします。
その他に、神社にお参りをされた際に受けたお神札は、更に後ろに重ねてお納めするなどしています。
お神札の数が増えて、宮形にお納めすることができなくなったときや、宮形に入らない大きさのお神札は、宮形の横に丁寧に並べておまつりします。
また、宮形を用いずにおまつりする場合も上記にならって丁重におまつりします。
お神札(ふだ)を取り換える
年の暮れには、神棚もきれいに掃除をして、新しいお神札をおまつりして新年を迎えます。
古いお神札は、一年間お守りいただいたことに感謝申し上げてから、お神札を受けた神社の古神札納所等へ納めます。
そして、お焚き上げをしていただき、新しいお神札をお受けします。
多くの神社では、大晦日から一月十五日(小正月)までの間に左義長やどんど焼等が行われ、正月飾りなどとともに古いお神札や、お守りなどがお焚き上げされます。
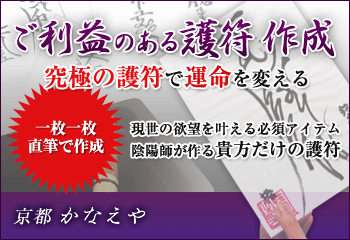
『お守り』とはどういうものですか?
護符、お札これらをまとめてお守りということもあり、比較的身近にあって気軽に身に着けて持ち歩いたり、車につけたりと様々です。
しかし、良く考えてみるとこれほど神妙で霊験あらたかなものはないのではないかと思えてきたりします。
お守りには、
- 厄除
- 良縁
- 安産
- 交通安全
- 学業成就
など様々です。
そして、お守りは常に身につけておくことでご利益を授かることができるといわれています。
文献によると、次の様に解説されています。
- 護符
- 霊符
- 守札
- 守護札
などともいう。
- 神名
- 仏
- 菩薩
- 諸天
- 鬼神の像
あるいは
- 種子 (しゅうじ)
- 真言
などを書いた札符で,これを持つものは神仏などに守護されるとしてこの名がある。
種類は祈願の目的によって種々あり,
- 火難除
- 盗難除
- 厄病除
- 安産
の守りなどがある。
所持する方法も種々あって,
- 肌身離さず持つもの
- 腹中に飲み込むもの
- 室内に安置するもの
- 戸や柱に張付けるもの
などがある。
出典|ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
お守りはどこにあるのが一番?
お守りは、身(車などを含む)につける方法と家などに祀る方法があります。
- 神様のご利益を授かるために、かばんや財布などに入れて常に身につけるようにする
- 家で保管する場合は、タンスなどにしまわず、目に付く場所へ出して、なるべく高い場所へ置く
のが良いとされているんですよ。
お守りはいつ交換するのが良い?
お守りは1年ごとに、新しく変えるのが一番。
新しくて綺麗なお守りは神の力が強いと考えられているようです。
普段から身に着けておくお守りだから、だんだん古くなると汚れ穢れる、すると神の力が弱くなる殻などといわれています。
護符お札お守り違いはなんですか?
https://www.instagram.com/p/BZuieiolCmG/?tagged=%E3%81%8A%E5%AE%88%E3%82%8A
護符・お札・お守り、このそれぞれの共通点は『神頼み』というところにキーワードがある。
しかし、同じ神頼みでもそれぞれに手段・目的・用途等に微妙な違いがあるのです。
- 手段では、どのようにして発行されるのか
- 目的では、何のために何をお願いするのか
- 用途としては、その御利益を受けるにはどのようにしたら良いのか
というように区分できてくるのではないでしょうか。
そして、最終的には『大願成就』、神様にお願いしたことが如何に叶えられるかという、共通した結果を期待するというものとなっています。
護符お札お守りはどんな風にして発行されるの?
護符の場合は、何らかの呪力をもった人が発行するとされています。
御札は、寺社仏閣等で神事に基づいて発行するといわれています。
お守りは、願い事が書かれた物を袋等に入れて、寺社仏閣などで発行したものが販売されている。
護符お札お守りにはどんな目的があるの?
目的としては、大願成就が究極の達成結果になるのですが、お願いする内容によってその違いがあるんです。
護符は、縁結び・恋愛成就などお願いする人のメンタルなことが中心で、身につけたり、貼り付けたりして祈願する。
- お札は、家内安全・商売繁盛等家庭や組織的なことが中心で、その多くは神棚に祀ったりして祈願する。
- お守りは、交通安全や学業成就などが中心で、袋状にした物を見に付けて安全や保身等文字通おりお守りしてもらうと祈願する。
と、いうように大別されるようです。
護符お札お守りにお願いする内容は多岐にわたり、祈願する人の気持ち次第で広範な心の拠り所にもなるようです。
護符お札お守りはどんな風に使うの?
用途的にも、それぞれに大きな違いがあるわけではなく、極論ではありますが、プロセスというよりも結果を重視した神頼みと言うもの。
護符の場合は、護符への願い事が達成されるまで日々祈願して結果を待つという、期待的要素を持つた用途が一般的。
お札の場合は、護摩を焚くというように大願成就を神仏にお願いすることで、1年の最良の結果をお願いするという用途になります。
お守りの場合は、護符・お札両方のいいとこ取りではありませんが、一番一般的で身につけることで安心が得られるという常に持ち歩いて効果を得られるというものなんです。
護符お札お守り共通項は『神頼み』?
護符お札お守りの違いについて整理してみました。
それぞれに神頼みというところは共通点であり、その手段・目的・用途に違いがあるようでした、使い方や気持ちの持ち方でも違いはありそうです。
最終的に、何が良いという選択とそれぞれの解釈の仕方は個人差がありますので、あくまでも参考としていただければ次へのステップにつながっていくように思います。
まとめ
護摩お札お守りの違いについてまとめてみました。
目的達成に日々努力する頼みの綱或いは友として懐の奥底に、そして心に秘めた願いの成就に護符お札お守りがメンタル的に役立つようです。
どういうわけか、困ったとき等に『神様仏様』とつぶやいたりしてしまいます。
人間の深層心理に最終的に頼りとするところは、そこにあるようです。
護符お札お守りの違いというよりも、それぞれ究極の到達点は同じようです。







