え!護符が飲めるの?
いきなりこんな出だしで始まりますが、今回のテーマは『護符飲み方』。
そもそも護符やお守りなどというものは、身につけて或いは貼り付けて、大願成就を祈願して真摯にお願いすることでご利益を得られるというのが一般的考え方です。
しかし、護符をちぎって飲むことでご利益を得るという仕方があるのです。
護符飲み方と種類、その効果について紹介していきます。
Contents
飲む『護符』なんてあるの?!
護符を飲むということの前に、なぜそうのようにいわれ始めたのか、そして本当に飲むことでご利益が得られるのか考えてみたいと思います。
護符を飲むといことは、そもそもは四国八十八ヶ所霊場と弘法大師から始まります。
四国八十八ヶ所霊場と真言宗
https://www.instagram.com/p/BZ-Y0lHDALX/?hl=ja&tagged=%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E5%85%AB%E5%8D%81%E5%85%AB%E3%83%B6%E6%89%80
弘法大師空海が、護符を水に浮かべて加持水(霊水)を病人に飲ませて病気平癒を成就させたという数々の伝説から始まったようです。
空海とは四国讃岐に生まれ、平安前期に真言宗を開祖して、弘法大師と称しています。
改めて言うまでもなくその功績は、最澄と並ぶ平安仏教確立の者としても有名な僧です。
そして、空海の護符を飲ませた加護が数々の伝説に始まり、四国八十八ヶ所霊場や真言宗の寺院を中心に現在まで多くの霊験を現し、今に伝わる護符の一つとなったようです。
- 徳島(阿波)の霊場 ~発心の道場~ 23箇所
- 高知県(土佐)の霊場 ~修行の道場~ 16箇所
- 愛媛県(伊予)の霊場 ~菩提の道場~ 26箇所
- 香川県(讃岐)の霊場 ~涅槃の道場~ 23箇所
飲む護符『千枚通し』
護符を飲むということの始まりを四国八十八ヶ所御霊場と弘法大師ということで説明してきました。
飲む護符の所以をたどると『千枚通し』という名が出てきました。
この伝えは、弘法大師が、足の不自由な人が苦しんでいるのを見て『千枚通し』という霊符を作って差し上げたところたちまち全快したと言うものとして紹介されています。
そして、このことにより千枚通しの名が全国に広がり千枚通し本坊として有名になったというものでした。
さらに、この千枚通しを今でもいただくことで、病苦を除いたり安産にご利益があると言い伝えられています。
千枚通しとは、どうやら弘法大師空海が奉じた護摩を言い、真言宗の教えににも共通し、飲む護符『千枚通し』と言うようになったのです。
10年に一度配られる『赤札』?
赤札とは、弘法大師ご直筆と伝わる『南無阿弥陀佛』の六字名号を版にして、当山貫首が精進潔斎のうえ、祈願をこめて一躰ずつを手刷りにされる尊いものとされています。
正式名称は『真言宗・智山派大本山・金剛山金乗院・平間寺』という神奈川県の川崎大師で、10年に1度のご開帳で配られる、入手困難な最強のお札『赤札』。
その『赤札』は、期間中のいつ、何時頃から授与されるかわからないという、御開帳の日に参拝して並んで待って初めてもらえるという大変貴重な護符といわれているのです。
丸めて粒状の護符『一粒符(いちりゅうふ)』?
帝釈天も ぶらぶら。 pic.twitter.com/JapuuwhWzl
— ヨッピー先輩 (@SJq3bb0kL9ki0r1) 2017年10月6日
お経を書いた和紙を丸めて『一粒符(いちりゅうふ)』という飲むお守りを病人に飲ませたところ、不思議に完治したなどともいわれている護符もあります。
少々変わった紹介ですが、みをつくし料理帖『花散らしの雨』の一説に
『柴又の帝釈天さまの護符のこと・・・確かあそこの一粒符てえお守りは病にご利益があると・・・。』
『一粒符は、・・・極めて小さな粒状の護符で・・・。』
『帝釈天さまから汲んできた水だ。むせねえように、ゆっくりのみな。』
みをつくし料理帖『花散らしの雨』(高田郁作)から抜粋
というように記述されています。
一粒符は
- 水と一緒に飲むこと
- 飲むと帝釈天の加護がある
- 飲むタイミングは自由で、体調がすぐれないとき、緊張やプレッシャーに負けそうなとき等に飲むと良い
というような説明がありました。
一粒符は、麻疹限定の御守りではなく、どの病気にもご利益がある、万能の御守のようで、飲むことでご利益を得ると言われている柴又帝釈天でいただくことができる『飲む護符』ということになります。
護符の飲み方には作法流儀があるのですか?

そんな護符ですが、飲み方という作法流儀はないようですが、飲みやすくして飲むというのが一般的のようですが、護符の下の方からちぎって飲む飲み方や
- 頭痛がするなどの時は、上の文字から
- 足が痛い時は下の文字から
- お腹が痛い時は、真ん中から
などという飲み方をしている人もいるようです。
しかし、飲む護符は薬ではありませんから薬効などを期待した利用は、間違いですから気をつけてください。
- 頭が妙に重い
- 肩が重たい
- どこかへ行った時、なんだか変な感じがする。
等といった症状という症状を感じ、気持ち的に不安定な状態があるというようなときに、ご利益ご加護を得るなどと精神的負担を軽減させる効果が期待できるというもの。
そのことで、治ったなどという人も稀にあるようですが決して薬的効果ではなく、何らかの精神的作用による効果になります。
そして、飲み方としては『南無大師遍照金剛 (なむ だいし へんじょう こんごう )』と例え、通常の場合は3枚をとり、おだいもくを三回唱えます。
そして、東を向いて。
東がわらない場合は、そのままで『なむだいしへんじょうこんごう』と三回唱え、小さくおってお水で飲みます。
疳の虫退治の護符の飲み方
かんのむしをとるなどの場合は護符3枚を取り、おだいもくを唱えてお子さんの口に折らずに食べさせる感じで飲ませます。
1枚でもかまいません。
そして、おだいもくをあげた後、頼み事を言います。
しばらくすると、爪の間から白い繊維のようなものが出て来ます、などといわれています。
大人の護符の飲み方
大人の方が飲む場合で、
- 体が重たい
- 生あくびが出て来る
そんな時は、
- 護符を5枚取り、
- おだいもくを5回唱え、
- 自分の頼み事を言ってから、
小さく折ってお水で飲みます。
このように護符の飲み方もいろいろあり、お題目を唱えるなどと説明されていますが、護符は、宗教とは関係ありません。
お護符を飲んでも、スッキリしない場合は、病気かもしれないので、病院へ行くようにしてください。
安産祈願の飲む護符と飲み方
10月8日
続いては水天宮さんに行かせていただきました!
水天宮には子供づれの家族の皆さんが多く参拝していてとても赤ちゃんが可愛かったです☺️
ここの御朱印はなんか味がありますね! pic.twitter.com/gfyvpRvyXZ— 🍙まさと@御朱印垢🍙 (@masato__goshuin) 2017年10月8日
近年の女性の第一子出生時平均年齢が昭和50年が25.7歳平成27に至っては30.3歳と高齢出産化の傾向が統計的に説明されているように出産への心配や不安を抱いている人もいます。
昔から安産祈願は、神事的儀式にもあり御札やお守りなどによる安産のお願いをしてきました。
そんなことで『ちぎって飲む』お守りが安産祈願で知られるよになり、水天宮の護符などが有名です。
東京日本橋にある『水天宮』は、安産祈願や子授けのご利益で知られる神社。
福岡県久留米にある水天宮の総本宮『久留米水天宮』の分社です。
祭神には日本神話に登場する神『天御中主大神(アメノミナカヌシノカミ)』とともに、平清盛の妻『二位の尼』や『建礼門院』建礼門院の息子『安徳天皇』が祀られているところ。
妊婦向けの水天宮御守『護符』には、『神呪(しんじゅ)』と呼ばれるまじないが和紙の上下左右中心の5箇所に配されています。
大寒に汲んだ筑後川の水に7日間の祈祷を行って作られた『神水(しんすい)』が使われた墨汁で、版木を使い印字されています。
これを中心から『の』の字の順に一文字ちぎり、水に浮かべて飲むことで、妊娠に伴う体調不良や陣痛を和らげると言われているんですよ。
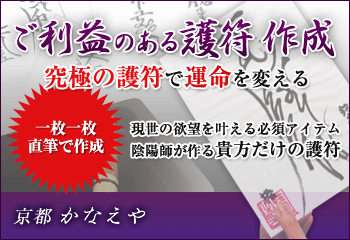
護符の効果・効きめは?

改めて『護符』の効果について考えてみたいと思います。
護符の効果そのものは、科学的に証明されたものではなく、その人のメンタルな部分いわゆるその人本人の気持ちに大きく変化をもたらすという効果への期待感。
願いが叶うという希望を持って神仏に祈願して、護符・お守りとしてその念を込めてつくられたものを身につけ、或いは祀り大願成就という結果にその効果を求めるものです。
そして、その最高の結果を得られるには、その人の信心の気持ちの大きさでも違うのです。
そして仏教の各宗派にも護符はあります。
真言宗や日蓮宗などの荒行がある宗派は、密教の部類になるので、護符や霊符の効果も大きいといわれているのです。
神社や陰陽道の護符も、300種類以上あるといわれています。
- 身につけることでご利益が得られる護符
- 祀り、貼り付けることでご利益があられる護符
- 飲むことでご利益を得られる護符
などがあります。
しかし、護符の効果は具体的にどこが治った等というよりも『願』を掛けることで、その願いが叶えられるという心の拠り所として又、その人の気持の中で効果が現れるものと言われています。

護符への強い思い入れと日々の祈願
昔から陰陽師・修験道などの呪術の能力を有すると言われる者が護符を授けています。
また宗教の多様化により寺社仏閣でも授けるようになり、祈願の内容も様々のようです。
護符は、
- 御符
- 霊符
- 呪符
- 神符
などと呼ばれ、『お札』『お守り』などともいわれ、割りと身近にあります。
そして、一般的には
- 交通安全
- 家内安全
- 身体健康
- 学業成就
- 商売繁盛
- 恋愛成就
など、幅広いお願いに仕方があります。
護符は、求める人の『願望や悩み』に合わせて様々な種類があるのが特徴です。
その数300種類以上ともいわれています。
護符に効果があると言われている理由には、このように願い事の細分化と願いに応じた『文字に強い意味と念』が込められているからともいわれています。
また、お札・お守りなどと違い、護符はただ身につけるだけでなく、護符をいただいた人も祈願成就に強い意思を込めて日々お願いするということも大切と言わています。
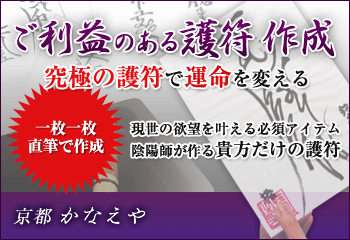
まとめ

護符の飲み方というよりも護符を飲むことで何の効果があるのか。
そして、飲む護符のいわれなどまとめてみました。
弘法大師から始まったという千枚通しという飲む護符の始めなどに触れながら護符への思いと大願成就のための所作などまとめてみました。
護符そのものは、宗教でも薬でもありません。
祈願することで心の拠り所であり、大願成就への羅針盤になるというもののようです。
護符飲み方の紹介でした。








